1 コシヒカリのレンゲ緑肥栽培(9年目)
(1) 2022年産の準備作業として
・ 2021年9月 25 日:耕耘=稲ワラの全量すき込み。
・ 〃 9月 27 日:全90アールにレンゲ播種。30アール当たり2kg。
(2) 2022年2月9日:第1回耕耘(レンゲすき込み)=60a(南田、北田)。
〃 東田は、レンゲ生育悪く、後回し(3月12日まで育てて、すき込んだ)。
(レンゲすき込みの様子=2015年)
(3) 3月21日、27日:第2回耕耘
(4)4月13、14日:代かき、全90a。
(5) 田植え:4月22,23日。農協から購入苗、45箱/30a当たり。
(6) 除草剤施用:5月8日、9日。カイリキzフロアブル、500ml/10a。
(7) 生育状況(主に、レンゲ緑肥1年目=東田の様子)
・ レンゲ緑肥1年目の東田は、緑肥効果が出るのが大分遅れているようで、
田植え後約1ヶ月。周囲の田より 黄ばんで見える。
 |
東田 ←この黄ばんだ田 ←これはよその田 |
| 東田:5月28日の状況(右が我田) |
・ 6月9日:茎の強化のため、3田に珪酸加里20kg/10a、施用した。
 |
←黄ばんでいた田が ほぼ周囲の田と同じ葉色になった ←進んでいた、よその田 |
|
| 6月19日 |
・ 穂肥7月8日:各田に 有機追肥530特号 13g/10a施用。1週間ほど遅かった。
・ 7月15日ごろ:出穂の走り
・ 出穂最盛期:7月23日ごろ
 |
右:東田 | |
| 7月23日 |
 |
東田:8月18日の状況 倒伏も無く、順調。 刈り取りまで12〜13日。 |
・8月18日:刈り取りに向け、貯まっている水(上の写真左隅に貯まっている水が見える)を落とし、
同時に、暗渠も水抜き。しかし、どういうわけか 暗渠水抜け悪く・・・後12〜13日で乾くかと気がかり。
・8月27日刈り取り。しかし、気掛かりだった田面が乾かず。更に前日〜夜の降雨(約23mm)もあって
(株)新田野ファームの大型6条刈りコンバインで、深い轍を作りながらの刈り取りとなった。
※その轍を埋めるのに、数日計8時間程かけて、大汗をかきながらの手作業となってしまった。
 |
レンゲ緑肥9年目の南北田 良い実りのため、少し倒伏。 8月18日の状況 |
(8) 刈り取り:8月26、27日。その翌日籾摺り。
(9) 収量:3田平均=440kg/10a、とマズマズ。
しかし、この収量を千葉県平均544kgに比べると約80%の超低収。
※倒伏しやすいコシヒカリのレンゲ緑肥栽培では、この程度が限界かも。
(10) 販売出荷・・・・・8月29日開始
価格=前年並み。
(次年産準備作業)
・2022年9月15日南北田耕耘:稲ワラ、全量すき込み。ほぼ順調。
開始遅れて13時半頃〜休み無く、18時半頃まで暗くなるまでかかってしまった。
・9月16日:問題の東田:田面軟弱でコンバインの轍が残っていて、大丈夫かと思いながら、しかし、
南方から本土をうかがっているT14の影響で、天気があやしいので、
とにかくその前に耕耘しようと、10時過ぎに耕耘開始。
まだ、田面がやや軟弱だったが、気をつけながら13時ごろ終了。良かった、良かった。
・9月25日:レンゲ播種(90a)。
前24日T15崩れの大雨(60mm)で、東田にはかなり水が溜まっていたが、
数日で引くだろう、南北田は水溜まり少なかった。3田とも同じように手播きした。
2022年縄文米(古代米)の遊喜栽培(14年目)
―――――――――――
・栽培開始当初は、ザリガニが多発し雑草を食害したので「遊喜ザリガニ農法」と洒落こんでいたのに、
最近は、ザリガニ に代わって「ジャンボタニシ」が蔓延、植えたての苗を食害し欠株も。
(1) 耕耘:2月8日。田面が乾いているうちにと、ゴムタイヤのままで耕耘。鉄車輪への交換は重くて大変なので、
ゴムタイヤで出来て良かった。その後、水を溜め、
・2月16日:手作業で均平化。
・4月3日:種子の水浸。
(2) 播種:4月16日。
(3) 5月3日:ジャンボタニシ駆除のため、石灰窒素施用。約7.5kg/2a。・・・・全滅させた。
(4) 5月9日:手作業で代かき。手作業では余り均平にはならなかったが、ある程度少しは代かきをしたようになった。
(5) 田植え:5月15日。
・代かき不十分で、浮き苗多数。
(6) 生育状況
・石灰窒素の施用で全滅させたつもりだったのに、卵には効かないのかジャンボタニシ多発生。
・・・・・分げつ少。欠株多・・・・・この分では低収(40kgかも)。
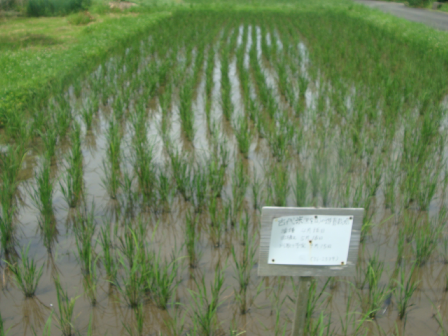 |
6・19日の状況 |
 |
ジャンボタニシの食害による欠株 (6.19) |
 |
出穂の走り (7・23) |
|
 |
8月18日の状況 少し欠株あるも、実り良さそう。 |
(7) 刈り取り:9月13日。
(8) 脱穀:9月14日。リヤカーで運んでは足踏み脱穀という方法で3回に分けての作業。
11時ごろ〜18時ごろまでかかって終了。その後、乾燥させるため、作業場の2階に広げた。
(9)籾摺り:9月21日:少し晴れたので籾の一部約1/7を、シートで庭に天日干し。
9月23日:水分率15%台に下がったので、当面のサービス用に、急いで籾摺り。9.3kgを得た。
10月2日:第2回籾摺り。25.5kg。
(10) 収量:67kg
この6年間で良品質2年に対し、不良4年という残念な結果。
 |
|
| 2018,19,20、2022年産 2017、21年産 |
この品質の差の原因は何かと、気象条件との関係を検討した。
(検討結果) 縄文米の品質と登熟期の気象条件との関係
(その際、コシヒカリの乳白粒発生原因についても、少し検討した)
※品質不良の原因は、登熟中期における高温多照。つまり早い話が「高温障害」。
(12)販売価格・・・(前年並み)
| 区分 | 量(g) | 価格(円) | 2023.1値下げ |
| 1 | 360 | 500 | 400 |
| 2 | 800 | 1000 | 800 |
(13) 縄文米栽培一連の作業、炊き方〜効能など
目次へ