コシヒカリのレンゲ緑肥栽培12年目)・・・(千葉エコ米20年目)
(準備作業)
・2024年9月8日:3田(90a)耕耘。ワラ全量をすき込む。、
・9月28日:レンゲ播種(90a)。
・2025年1月31日:レンゲすき込み。
3田ともレンゲの生育良く、育ち過ぎると水稲の倒伏の恐れがあるので、大分早いが全量すき込んだ。
・3月19日:水入れ後、漏水防止のため南北田の畦畔際の耕耘。
・3月27日:南北田の漏水止まらないので、畦畔際を耕耘。その後、東田の耕耘。
それぞれ、漏水ナカナカ止まらず。
・3月30日:3田の畦畔際を漏水止めのため耕耘。
(1)代かき
・4月13日:3田の代かき ※漏水ようやく止まった。これで大丈夫そう。
(2)田植え
・4月19日:東田へ予定より早く15時ごろ農協から苗が届いたので、早速植え始め17時45分頃植え終わった。
午後南田へ、そして北田と一気に植え、18時30分終了。
・4月21日:北田を10時過ぎ〜植え、南田を13時45分〜植え、16時終了。
その後、U字溝に用水が来ていたので都合良く育苗箱洗い、路肩で乾かす。
・4月22日:午前中かかって昨日植えた田の4隅を中心に補植。
午後、育苗箱を農協へ返しに行き、これで、コシヒカリの田植え作業は終了。
(3)生育状況
・5月7日:除草剤施用。前日の雨もあって適水量。漏水も無く、安心して施用した。
・5月18日:3田の生育状況を点検。周辺の田に比べると貧弱だが、レンゲ緑肥は遅効きなので、この程度でマズマズ。
しかし、畦畔際にジャンボタニシ多数発生、手で届く範囲を捕殺したが、これはまさに気休め。
 |
5月26日、東田の状況 緑肥のレンゲが遅効きなので、初期 生育不良もあって、周辺の稲に比べ ると、前方が黄ばんで見える。 しかし、2022年程の酷さではなく、 マズマズというところ。 |
・ 追肥:5月25日、珪酸加里を、約9kg/10a施肥。
・ 穂肥:7月6日、有機追肥530特号を、約9kg/10a施肥。
レンゲ生育ムラで、列状の稲の生育ムラ対策で、生育不良部分に重点的施肥した。・・・これが失敗。
 |
レンゲの生育ムラによる稲の生育ムラ 左南田。右北田 南田の列状に黄ばんでいたところが、 重点的穂肥で、逆に濃緑になってきた。 (7月12日の状況) |
 |
8月6日の状況 重点的に穂肥を施用した箇所が 効き過ぎて、倒伏した。(南田) |
 |
収穫始めの「国吉耕地」の状況 (2025.8.6) 今年は、米不足値上がりで 飼料用の稲玉は見られない。 (参考)2024年は、白い稲玉が 多数見られた |
(4) 収穫・・・・本25年は特別な猛暑カラカラで、我がコシヒカリも超早熟。予定より数日も早い刈り取り。
しかし、地球温暖化が進んでいるので、今後はこれが普通になりそう。
・8月20日:刈り取り〜乾燥。
・ 〃21日:籾摺り調製。
・収量:30kg139袋/90a=463kg/10a・・・反当7.7俵、マズマズ。検査も問題無く1等。
・試食:例年どおりの美味。
(5) 次年2026用準備
・ 耕耘:9月7日。
・レンゲ播種:9月16日。種子3kg/30a・・・(2026年〜作付け1/3に減少予定)
2 2025年産縄文米(古代米)の遊喜栽培(17年目)
―――――――――――
・栽培開始当初は、ザリガニが多発し雑草を食害したので「遊喜ザリガニ農法」と洒落こんでいたのに、
最近は、ザリガニ に代わって「ジャンボタニシ」が大繁殖、植えたての苗を食害して困る。
(1) 耕 耘: 1月5日と24日。田面が乾いているうちにと、ゴムタイヤのままで耕耘。鉄車輪への交換は重くて大変なので、
ゴムタイヤで耕耘出来て良かった。その後、水を溜めて手作業での代かきなどに進む。
※ 種子の更新:前回の更新後5年経って種子が劣化したためか、一昨年、昨年と産米が茶褐色に色褪せた粒になってしまったので、
今度は晩生の「さよむらさき」に更新した。
・・・昨年までの16年間は、何回か更新しながら早生の「朝紫」を栽培してきたのだが・・・さて、今年の品質は如何に・・・
・3月31日:種子の水浸。 ・・・その後、4月5日〜7日お湯に入れて=芽出し。
(2) 播 種:4月9日。育苗箱5箱に播いた。苗の生育は順調で、均平に育ったが、どういうわけか一部に黄ばんだ所も。
(3) 5月5日:手作業で代かき。
ジャンボタニシ駆除のため、石灰窒素施用。約5kg/2a。
(5) 田 植え: 5月12日。
手作業での代かきでは、田表面の土が硬くゴロゴロしていて、苗が土によく挿さらず浮き苗多数。
田植え機による田植え時間は15分程度だったのに、補植に2〜3時間かかってしまった・・・。
しかも、この後、田植え機洗いや注油などの手入れもあるし・・・全部手植えでやった方が早そう。
※ しかし、田植えは、機械で植えたり手で植えたり、泥で汚れたりが楽しいのだ。
 |
田植え翌日の状況 浮き苗多数 (2025/05/13) |
(6) 生育状況
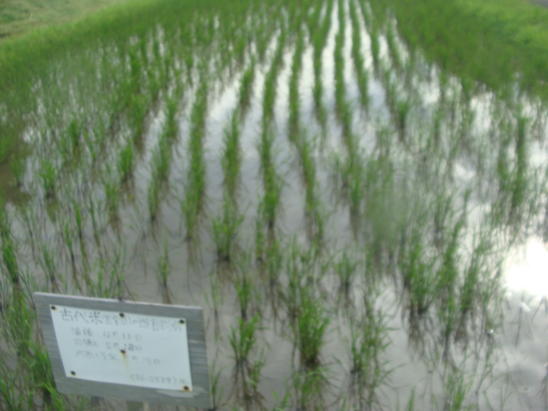 |
田植え後、1ヶ月余り 元気に生育中 (6月15日) |
 |
7月7日の状況 |
・ 異品種が混入したようで、7・12に数株出穂していたので引き抜いた。その後も、7・23,7・28にも数株ずつ引き抜いた。
この古代米は晩生なので、出穂はまだ先。
・ 出穂を前に葉色が少し黄ばんでいるが、無肥料栽培なのでやむを得ないところ。
(7) 出 穂:8月15日頃〜ようやく出穂始まる。しかし・・・
その後9月6日までの大事な時期に、雨なし猛暑カラカラお天気が続き、さすがの湿田も乾いて登熟不良。
 |
刈り取り直前の穂の状況(9.21) 稔り悪く、かつ不稔率約50%ではコウベも下がらず ・・・・枯れそう・・・・ |
| ※ 日照りにて 会釈程度の 稲穂なり ※ |
(8) 刈り取り:9月22日。・・・21日予定が、その前日の雨で湿ったのでこの日に行った。
バインダーの結束紐が、紐の出口で絡んだりして手間取り、刈り取りに
約1時間かかってしまった。
(9) 搬 入:9月23日午後、前日〜田に刈り干し=天日干し。反転したりして乾かしたものの生乾きだったが、
その稲束を、15時ごろ〜作業場の庇に、例の4輪リヤカーで搬入。
・・・穂が軽いのに逆に駄が多く、稲束数は385と超多(数えた)・・・例年は約270束。
※今後、この稲藁は畑の敷き藁等で1年中役立ちそう。
(10) 脱 穀:9月27日
 |
足踏み脱穀場の様子。 手前は藁の山の一部分、 軽トラック荷台は脱穀待ち稲 カメラマン不在:自撮りも出来ず |
・・・その後、藁も籾も天日干し・・・ そして、風選。→飛散した不稔籾が山を成した。
(11)籾摺り:10月5日、第1回目約1/4.5を行い8.2kgを得た。→収量は推定37kgとなる。
(12) 収 量: kg。くず米除去の篩い選別を行わないので、少ないながらも、それなりの収量。
(13) 品 質:小粒な上に、下写真↓のような着色不良。薄色の赤飯になりそう。
この品質不良は、特に登熟期の雨無しカラカラ続き、水無しが大きく影響したものと思われる。
 |
|
(14) 縄文米の炊き方効能など
目次へ